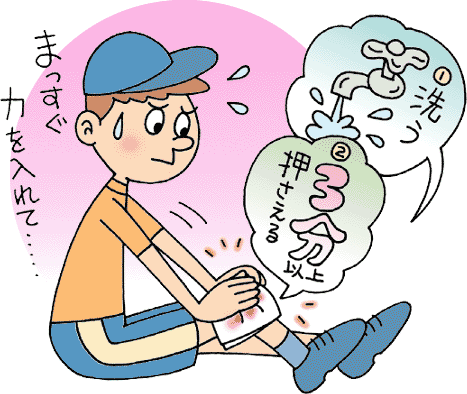
治療法
破傷風の治療法としては、早期に診断して十分な量の抗毒素血清を投与するのが望ましいのだが、潜伏期があるために初感染創が完全に治癒してしまうこともあり、本人に自覚がないままに症状が現れてくることもある。
細菌の増殖を防止するために、創傷はできるだけ開放性にして、組織内の異物は完全に除去しなければならないので、菌の侵入部位と考えられる創傷が存在するときは、外科的切除によって壊死の部分や異物の排除を行わなければならない。深い刺傷の場合は、泥や死んだ組織が破傷風菌の増殖を促進してしまうため、素早く徹底的な消毒を行う。
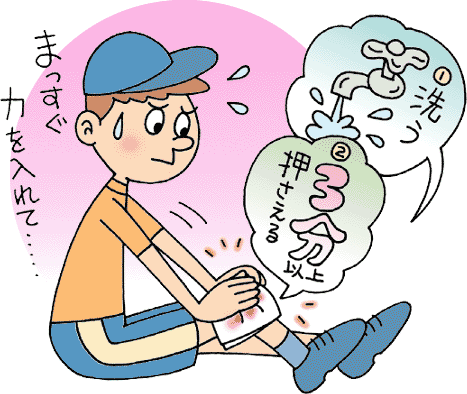
■傷口を洗浄し、患部を押さえる
まずは、傷口の泥や砂などの汚れを、きれいな水で洗い流します。きれいな水がない場合は、お茶やジュースなどの清涼飲料水でもかまいません。そして止血します。止血の基本は次の通りです。この方法で、ほとんどの出血は止まります。
・傷口に布(清潔なタオルやハンカチ)を当てる
・布の上からまっすぐ力を入れて、3分間以上押さえ続ける
・押さえている途中で手をゆるめたり、傷口をのぞいたりしてはいけない
・灰やみそ、よもぎの葉といった、民間療法は行わない。何の効果もなく、かえって傷の治癒を遅らせてしまうことになる
■それでも出血が止まらない場合
傷口の根元を縛ったり、傷口からなるべく心臓に近い動脈を押さえるなどして、すぐに医療機関へ行きましょう。ただし、長い時間、縛ったままにしていると、そこから先の部分が壊死してしまうこともありますので、できるだけ早く治療を受けることが大切です。
各時期の治療と看護のポイント
第Ⅰ期
<
治療>・過酸化水素水で創部の洗浄をし異物を除去する
・
破傷風免疫ヒトグロビンを与える・抗生物質を大量に与える
<
看護のポイント>*
受傷時の経過を正しく把握する・いつ、どこで、どんな状況で受傷したのか
・その時、創傷の処置はどのようにしたか
・予防接種は受けていたか
・受傷後に破傷風免疫ヒトグロブリン、破傷風トキソイドの注射を受けたか
・症状が出現したのはいつからか
*
症状の増悪、進行の状態を観察し早期に対処する・開口障害の程度をみる =)口を開いてもらい、歯と歯の間に指が何本入るか、その程度の変化を目安とし観察する
・嚥下困難や会話困難がどの程度進行しているか
・頚部硬直の進行はどの程度か
・引き続き出現する症状を早期に発見する
*
環境の準備を行う・緊急事態に対処できるように物品の準備確認をしておく
第Ⅱ期
<
治療>・応急処置可能な
個室またはICUに収容する・気道を確保する
・
鎮静剤や筋弛緩剤を使用する・静脈路を確保する
・留置カテーテルを設置する
<
看護のポイント>*
部屋の環境を適切に整える・外部からの刺激をできるだけ遮断する(暗幕、カーテンなどで光刺激を遮断し、騒音を防止)
・ベッドからの転落や四肢、頭部の打撲の危険がないようにベ ッド柵や枕を利用する
・処置やケアは
短時間で手際よく計画的に行い、皮膚への刺激を 最小限におさえる・面会人を制限する
*
症状の増悪の観察・外部からの刺激によって
筋痙攣が増強し、呼吸停止や心停止 が起こる可能性が強いため頻回に症状の観察を行う・血圧、脈拍、
意識状態をチェックする。特に呼吸数、呼吸の深さ、胸腹部の動きに注意を払う =)心電図モニター、自動血圧計の装着*
緊急処置にすばやく対応する・予想される緊急処置に備えて、必要器材がすぐに使用できる状態であるかどうかの点検を綿密 にする
*
身体の清潔を保持する・異常発汗に対しては手早い清拭、寝衣・リネン交換を行う。皮膚への接触や体動が筋硬直を誘発するのを避けるために、寝衣は上から羽織る形のものにし、バスタオルを上下に敷き頻回に替える。背部清拭は2人以上、数人のナースで行う
・口腔内分泌物に対しては、適時吸引あるいは蒸留水や生理食塩水などでの洗浄を行う
*
合併症の誘因となる環境に注意し取り除く・吸引時の無菌操作
・処置前後の手指消毒
・留置カテーテルの清潔保持
・辱創に対しては、体位変換は
全身痙攣の刺激となるため励行が困難である事が予想されるので 背部清拭時のマッサージ 辱創予防マットレスの使用などを試みる*
精神的な苦痛、不安を和らげる・会話できない状態にあることを常に念頭におき、ケア及び治療時には必ず声かけをする
・手の動き、顔の表情、頭の動きなど患者の小さな反応の変化を見逃さない
・患者に励ましの言葉を書け、不安を少しでも和らげる
第Ⅲ期
<
治療>・呼吸を管理する
・血圧の著しい変動に対し循環動態を管理
・
高カロリー輸液の管理・合併症の予防
<
看護のポイント>*
異常を早期に発見する・血圧は著しく変動するので頻回に測定し、降圧剤、昇圧剤の使用に伴う効果を確認する
・意識状態の変化や持続している症状の増悪変化に注意する
*
必要機器の点検・加湿器の水分貯留の防止
・蒸留水の交換
・バクテリアフィルターの交換
・心電図モニター、自動血圧計、輸液ポンプの電極版や電池の交換
*
二次感染を引き起こす危険性の除去・期間内吸引においては痰の性状の、留置カテーテルにおいては尿の性状の観察を行うが、その際には清潔に注意する
・中心静脈栄養刺入部の観察においては、カテーテルの皮膚刺入部からカテーテルを伝わっての上行感染に注意する。刺入部はなるべくドライに保ち定期的に消毒する。刺入部の皮膚の発赤や発熱に注意し、もし認めたら直ちに医師に報告する
*
人工呼吸器使用による合併症の観察・人工呼吸器使用している場合はさまざまな合併症の危険がつきまとう(下表参照)適切な機器の取り扱いと注意深い観察を行い、予防及び早期に対応する
|
予想される合併症
呼吸器合併症
気管の損傷
気胸、皮下気腫
無気肺
水、電解質のアンバランス
心循環障害
酸素中毒
消化器合併症
|
徴候
発熱、白血球数の上昇 気道内分泌物の性状変化
血性分泌物の吸引 換気量の減少
呼吸困難、頭痛、疼痛 呼吸音の変化(減弱、消失)
発熱 呼吸音の変化(減弱、消失)
体重の増加 浮腫 血液ガスの変化
低血圧、尿量の低下 脈拍の変化(不整脈、頻脈、除脈)
胸痛(呼気時)呼吸困難 痙攣、意識の混濁
空気嚥下による胃拡張 ストレス性潰瘍 消化管出血
|
対応
無菌操作の撤退、回路の定期的交換 分泌物の定期的吸引
気管内チューブの位置を変える 低圧カフ、ソフトカフの使用
直ちに医師に連絡 胸腔チューブの挿入
頻回な体位変換や深呼吸 定期的な吸引
血液ガスと電解質のデータチェック 体重の変化、浮腫の観察 水分出納のバランス観察
水分出納のチェック 胸腔内圧を低下させるため 1回換気量の減少
血液ガスのチェック 酸素濃度のチェック、低濃度への切り替え
胃内チューブからの血性吸引物の有無 便への血液混入、タール便の有無 腹部膨満の有無 |
*
患者、家族への精神的援助・患者は薬剤により意識レベルの低下が見られるが、処置前後には必ず声かけを 行う
・家族に対して病状の説明、あたたかい励ましの声かけを繰り返し行い、家族との面会の機会を 多くする
*
高カロリー輸液の管理・感染予防のために刺入部の消毒を行い清潔を維持する
・輸液ルート、三方活栓の無菌状態の維持にも注意する
第Ⅳ期
<
治療>・自発呼吸の確立
=)ウィーニング(人工呼吸器を外すこと)の導入・呼吸器合併症の予防
・栄養状態の改善
・リハビリテーション
<
看護のポイント>*
ウィーニングの開始時期・呼吸循環状態の変動が起きやすいので注意する
・呼吸練習時には血圧の変動の有無、脈拍、呼吸数、呼吸パターン、1回換気量のほかに、患者の表情の変化、急激な発汗など一般状態の変化のチェック、血液ガス分析などのデータのチェックを行う
*
意識状態の観察・患者の反射を含む動作、四肢や指の動きの変化を見る
・声かけへの反応、表情の変化などに注意する
・不安感や苛立ち、苦痛などの訴えを観察し、これらが解消できるようにコミュニケーションを十分とる
・動脈血ガス分析結果に注意し、低酸素状態、炭素ガス蓄積症状に気をつける
*
栄養状態の観察・検査値を観察しながら徐々に経口摂取をすすめていく
・経口摂取開始直後は誤嚥に注意する
*
離床に向けての訓練・呼吸筋のリハビリテーション、呼吸訓練を行い、ベッド上での自動他動運動を計画的に進めていき、徐々に日常生活動作の拡大を図っていく
治療時に投与される薬
破傷風沈降トキソイド
:弱毒化した破傷風外毒素そのものであって、発生している破傷風には無効である副反応…発熱、注射部位の発赤。特に浅く皮下注したときに起き易い
1
回0.5mlを皮下注、もしくは筋注する破傷風免疫ヒトグロブリン
:発病した破傷風の治療として 投与するときは傷よりも近位部に打つことが望ましい。破トキと同じ部位に注射してはいけない
1回1mlを筋注するペニシリン
(抗生物質):G200万単位を静脈注射 6時間ごとに10日続けるテトラサイクリン
(抗生物質):500mgを静脈注射 6時間ごとに10日続けるルミナール
(鎮静剤):3~5mg/kgを筋肉注射か静脈注射ペンタールソジウム
(鎮静剤):0.4%を静脈内注射ロバキシン
(筋弛緩剤):初回用量50mg/kg/時間 筋肉注射か静脈注射 4~6投薬に分け3mg/分の割合で注入
参考文献
・クリニカルナーシング9「感染症患者の看護診断とケア」
/医学書院・医学各論11「感染症」/医歯薬出版株式会社
・「感染症ケーススタディ」/医学書院
・「感染症学」/医学書院
・看護観察のキーポイントシリーズ
「内科Ⅳ」/中央法規