
インフルエンザの感染経路
インフルエンザウイルスの感染は、原則として閉めきられた部屋や乗り物などの閉鎖環境における飛沫
(ひまつ)感染である。患者のくしゃみ、咳などによってインフルエンザウイルスを含む飛散微粒子の飛沫核となって排出され飛び散り、周囲数メートルの範囲内にいる人の鼻腔内に侵入する。そこでウイルス粒子表面にある血球凝集素が、上気道粘膜上皮細胞の表面にあるシアル酸レセプターに吸着して感染を始める。たとえば、侵入した1個のウイルスは感染してそこで増えて、約8時間後に数百から数千のウイルス粒子を放出し、2世代の増殖後の約14時間後には数百万個に達する。そして20〜50時間後に症状として39〜40℃の高熱が出て、頭痛、筋肉痛、関節痛などのいわゆるかぜ症候群の症状が現れてくる。そしてこの時期にインターフェロンが産出されインフルエンザウイルスの増殖を抑え、1週間後に鼻汁抗体、血中抗体による免疫力が揃い、合併症がなければ回復する。臨床的な症状の経過としては、1〜3日の潜伏期を経て39〜40℃の高熱を伴って急激に発症する。その際、悪寒、頭痛、背中や四肢の筋肉痛、全身倦怠感などの全身症状が多く見られる。やや遅れて咳嗽、鼻汁などの症状が出現してくる。有熱期間は3〜4日で、約1週間で治癒する。しかし、基礎疾患を有する者や乳幼児や高齢者では、二次的細菌感染や種々の合併症を引き起こし、死亡することがあるので、注意が必要である。


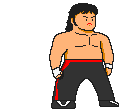
闘魂三銃士