
2.
HIVについてHIV
感染症とエイズ(後天性免疫不全症候群)エイズの病原体は、レトロウイルス科
( Retrovividae )に属するRNAウイルスである、ヒト免疫不全ウイルス(Human Immunodeficiency Virus, HIV)。このウイルスは
CD4+Tリンパ球に好んで感染して破壊するため、その減少による細胞性免疫不全(後天性)でエイズが発病する。
HIVには、全世界に広がっているHIV-1と,アフリカ西海岸を中心に流行しているHIV-2というサブタイプが知られている。HIV-2の塩基配列は、サル免疫不全ウイルス(simian immunodeficiency virus, SIV)に近く、人畜共通感染症の可能性がある。HIV-2感染の臨床症状は、HIV-1感染のそれより軽症なことが多い。
HIV感染による免疫不全が高度になると、結核やニューモシスチス・カリニ肺炎などの日和見感染症が合併する。近年、エイズ患者のKaposi肉腫は、ヘルペス8型ウイルスの感染が示唆されている。
さらに、
AIDS痴呆症候群(AIDS dementia complex)の様な精神神経病状のように、エイズは多彩な症候を呈する。
エイズは
1981年にアメリカで初めて報告された。初期には同性愛男性に、次いで麻薬静注常用者、血友病患者などに発病が広がり、これらは本症のハイリスク群とされた。病原体の同定は、1983〜84年にかけてフランス・パスツール研のMontagnierと、米国NIHのGalloによってなされた。
<
HIVの基本構造>
HIV-1の遺伝情報は約9kbのRNAに含まれている。レトロウイルスに共通の構造遺伝子として、 gag (コア蛋白),、pol (逆転写酵素),、env (外殻)の3つであるが、HIV-1にはこの他に調節遺伝子を数種類コードしている。HIV-2との違いは、これらの調節遺伝子の部分である。
HIV-1の主な標的細胞はCD4+Tリンパ球で、CD4+Tリンパ球表面のCD4蛋白がHIVの受容体となる。HIV-1がCD4+に結合すると、ウイルスRNA遺伝子はリンパ球の中に取り込まれ、ここでHIV-1の有する逆転写酵素によってDNAに逆転写される。
このようにしてできた
proviral DNAはリンパ球の遺伝子に組み込まれる。CD4+Tリンパ球の遺伝子が免疫的刺激により活性化されると、mRNA、ウイルス蛋白が順次つくられ、ウイルス粒子に組み立てられて感染リンパ球から放出される。この過程で、逆転写の際にエラーが生じやすいため,年間に塩基配列の0.5〜1%に変異が起こる。これがHIVワクチンの開発を困難にしている。HIV
の特徴として(1)
変異しやすく、特に外被の部分に変異が生じ易い。この特徴のためワクチン開発が難しくなっている。(2)
原則として一度感染すると持続感染し、一過性の感染はまれであるとされている。(3) HIV
抗体が存在すればHIVが存在する。
参照
http://www.coara.or.jp/%7Emako/qmed/aids/3b.html
<HIV遺伝子の解明>
ウイルスの増殖を止めるためには増殖サイクルにおけるターゲットを明確にする必要がある。このため、ウイルスの遺伝子構造とその変異、ウイルス粒子形成、遺伝子発現調節、ウイルス複製などについて詳細な研究がなされる必要がある。
HIV
-1(Human Immunodeficiency Virus-1:ヒト免疫不全ウイルス1型)の遺伝子については、レトロウイルスの基本遺伝子(gag, pol, env)はHIV−1の増殖に関しても必須であること、また、これらの構造遺伝子のほかにウイルス増殖に必須の遺伝子が2つ存在することが明らかとなり、この2つの遺伝子はtat, revと命名された。しかし、その他の
nef, vir, vpr, vpu遺伝子に関しては不明な点が非常に多く、また、これらの遺伝子はウイルス増殖に必須ではないともいわれているが、未だ明確ではなく、今後の重要な研究領域である。
HIV−1遺伝子の機能
| 遺伝子 |
機能 |
ウイルス増殖に必須 |
|
gag |
主要ウイルス構造蛋白 |
Yes
|
|
pol |
プロテアーゼ、逆転写酵素、リボヌクレアーゼH エンドヌクレアーゼ
|
Yes |
|
env |
ウイルス外被糖蛋白 |
Yes |
|
tat |
LTR に働く転写のトランス活性化因子 |
Yes
|
|
rev |
ウイルス構造遺伝子 (gag,pol,env)の発現促進 |
Yes
|
|
vif Env |
蛋白ウイルス粒子への取り組み促進 |
No |
|
vpr |
ウイルス増殖促進 (弱い) |
No
|
|
vpu |
ウイルス粒子の細胞外への放出促進 |
No
|
|
nef |
機能不明 |
No
|
参照
http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/aids/aids_search.html<
HIVの生体内感染形式>
HIV
の生体内感染は、細胞外の遊離ウイルスがCD4+Tリンパ球に直接感染する経路と、感染細胞が未感染のCD4+Tリンパ球と接触して細胞間感染を起こす経路がある。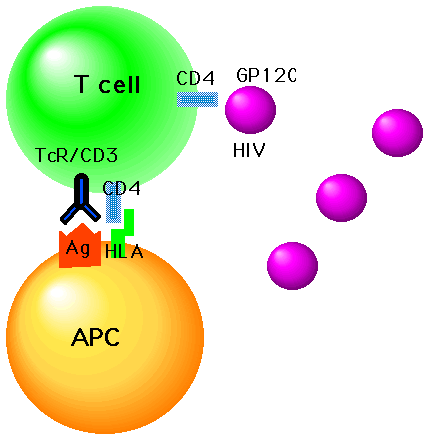
HIV(ウイルス)増殖のしくみ
HIV
ウイルスはその外被のエンベロープ蛋白(gp120)により、CD4陽性リンパ球の膜表面のHLAに対する受容体であるCD4と結合し、リンパ球内部へと侵入する。なおCD4受容体はリンパ球のみならず、マクロファージや脳グリア細胞、樹状細胞などにも存在し、これらの細胞にもHIVウイルスは感染すると考えられている。(上の図)
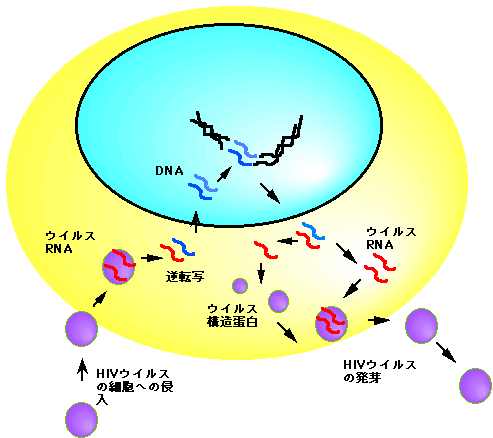
HIV
ウイルスはリンパ球内に侵入後、ウイルス特有の逆転写酵素を用いてウイルスRNAをDNAへ逆転写する。逆転写されたDNAは宿主DNA内に挿入される。(プロウイルスDNA)このプロウイルスDNAよりウイルスのゲノムRNAが転写され、またウイルスRNAからHIV構造蛋白が翻訳されて、HIVのウイルス粒子が複製され、発芽していくと考えられている。(上の図)
参照
http://www.amda.or.jp/contents/database/5-8/hiv1.html
<
HIV感染症の経過>
HIV
感染症の病態は次第に明らかにされてきた。無症候期は、HIVに感染しているがエイズを発症していない潜伏期とされてきたが、ウイルスは、半減期6時間という速さで増殖し、毎日100億個前後のウイルスが複製されている。増え続けるウイルスは、リンパ節などで新たに生産されるCD4陽性リンパ球に次々と感染し、感染したCD4陽性リンパ球は平均2.2日で死滅する。ウイルスの増殖と感染した
CD4陽性リンパ球数が次々と死滅するという、平衡状態が、やがて、ウイルスの増殖が優位に傾くと、CD4陽性リンパ球数が減少する。
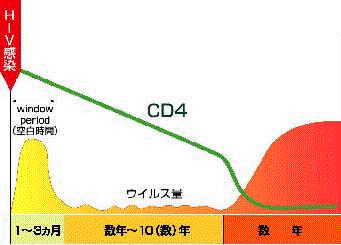
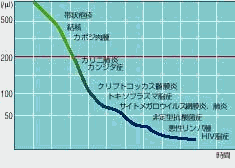
血中
1ml中のCD4陽性リンパ球数が200を下回ると、いろいろな日和見感染症が起こってきます。日和見感染症はだいたいどのくらいのCD4陽性リンパ球数で発症する可能性があるのか明らかになっています。参照
http://www.acc.go.jp/accpage/dokuhon/doku_kiso04.htm http://www.acc.go.jp/accpage/dokuhon/doku_kiso03.htm
<HIVと結核>
HIV感染者は性暴政免疫が低下するので感染していない人に比べて、再燃や再感染、発生のリスクは
10倍と言われている。結核はCD4陽性リンパ球数が比較的高いうちでも発生するリスクがある。HIVに関連した結核は、通常の肺結核のほかに播種性および肺外結核が多く見られる(粟粒結核、リンパ節結核、胸水、髄膜炎など)。
CD4陽性リンパ球数が200/リットル以上の場合は、HIVに感染していない人と同様の所見だが、CD4陽性リンパ球数が200/リットル未満の場合は、縦隔リンパ節腫大が多く、喀痰塗末検査で抗酸菌が陽性でもX線所見に異常がないことがある。また結核を発症することで、HIV感染が判明するケースも増加している。諸外国ではHIV感染者の多剤耐性結核が深刻な問題となっている。HIV感染者が判明した緊急入院患者などで呼吸器症状のある場合は、個室管理にして、胸部レントゲン、喀痰塗末・培養を行う必要もあるだろう。排菌が確認されたら周辺の結核病棟や空調管理のできる病床へ連絡をとり、対応を相談すべきである。
ツ反についても細胞性免疫の機能が低下しているため陰性の場合があり、結核菌や非定型抗酸菌のPCR法による迅速診断の活用が期待されている。
治療としては、HIV感染者の場合
9ヶ月〜1年と期間が長くなる。抗結核薬の副作用はHIV感染患者には多く出現するといわれており、また、リファンピシンは抗HIV薬の一種であるプロテアーゼ阻害剤の血中濃度を下げる相互作用があるので、HIV感染者への結核治療薬としては禁忌である。変わりに、リファブチンを通常の半量にして、プロテアーゼ阻害剤を増量する。まだ抗HIV薬の内服を開始していない患者には、服薬アドヒアランスの理由から、まずは結核の治療を導入して服薬状況が良好である事を確認する。そして抗HIV薬の開始の検討を行う。抗HIV薬も同時に開始する事は、錠剤数、服薬回数、副作用などの日常生活への影響が大きいため、容易に服薬中断したり、中途半端な服薬になってしまうためである。このように、HIV感染者の場合、結核治療を行う際には、留意点がある。HIV感染患者への結核予防教育としては、排菌者に接触しない事、結核感染の早期発見の観察ポイントなどを教育する。また結核発症はHIV感染症の進行を早める事も分かっている。
参照
「かんご」 2000年 7月号 日本看護協会出版