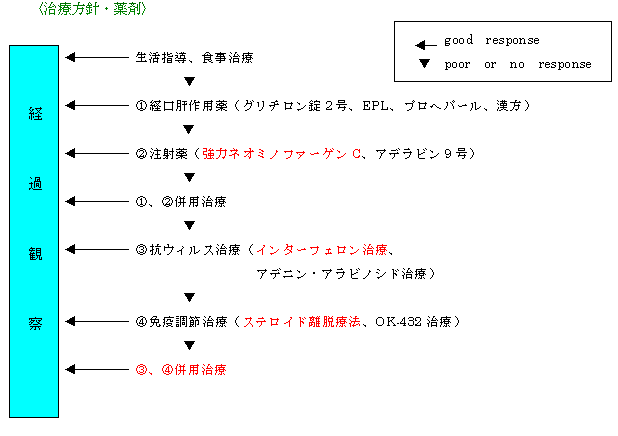
治
療
急性肝炎
原則的に一過性の良性疾患である為、特別な治療薬は要しない。一 般的には安静と必要に応じた補液等を行うのみで充分である。
安
静……臥位の姿勢を極力とる。(臥位は肝血流量が立位より多い。)有効肝血流量を増加させることは、急性障害肝に対して好影響を与える。
補
液……ブドウ糖(ビタミンを含む)――食欲不振にて摂食できない時。
プレドニン、ウルソエオキシコール酸――黄疸が強い時。
グルカゴン、インスリン――重症肝炎の時。
食
事……脂質を減らし、糖を中心とした、やや高蛋白なバランス良い食事。従来の高エネルギー、高蛋白食は、回復時に肥満を招く。
慢性肝炎
慢性肝炎とはウィルスによって、惹起された免疫反応による持続性の肝細胞障害である為、治療薬には作用機序より考えると大きく4種類に分類できる。
1.肝細胞保護作用を主体とする薬剤(肝作用薬)
2.免疫反応を抑制する薬剤
3.免疫反応を増強することによりウィルスの排除を狙う薬剤
4.抗ウィルス薬
主な作用
代表的薬物
①
グリチルリチン――慢性活動性肝炎の組織学的な改善②
肝臓抽出エキス(アデラビン)――GOT、GPT、γグロブリンの改善③
チオプロニン(チオラ)――GOT、GPT、ZTTの改善④
肝臓加水分解物(プロへパール)――肝組織呼吸促進作用、GOT、GPTの改善効果⑤
ポリエンフォスファチジルコリン(EPL)――GOT、GPTの改善⑥
ウルソデオキシコール酸(ウルソサン)――利胆作用、肝血流増加作用、胆汁うっ滞改善作用⑦
漢方薬――肝作用薬の単独投与のみでは、慢性肝炎の治癒は期待できない為、抗ウィルス薬、免疫調整薬との併用が望ましい。
2.免疫反応を抑制する薬剤
――副腎皮質ステロイドこの治療法は、以下の理由から、実際にはほとんど行われていない。
3.免疫反応を増強することによりウィルスの排除を狙う薬剤
免疫系を介しての坑ウィルス効果を狙う。
原
理副腎皮質ステロイドを短期に大量に使うことにより、宿主免疫能を抑え込み
B型肝炎ウィルスを増殖させ、その後 にこの薬剤を急速に中止することで、宿主の免疫能を賦活化し、B型肝炎ウィルス感染細胞を破壊することにより、ウィルスを排除したり、ウィルス量を減少させる。効果・副作用
高い治癒率を示す反面、副作用も強く、一時的にせよ肝炎を悪化させる治療法なので、治療途中で重症になる例もある。
1)
2)
シゾフィラン――胆癌生体の免疫能を賦活する。3)
インターロイキン-2(IL-2)――T細胞増殖因子4)
インターフェロン(IFN)-γ――マクロファージの活性化作用T細胞のIL-2レセプターの発現増強作用等免疫系への作用
IFN-
γは抗ウィルス作用は弱く、免疫調整薬としての作用が主体に考えられている。
4.抗ウィルス薬
①インターフェロン(
IFN)〈概要〉
インターフェロンは、身体がウィルスに感染した時に体内で作られる物質で、間接的にウィルスの増殖を抑える作用をする。インターフェロンがウィルスに感染した細胞と結合すると、その細胞がウィルスの増殖を抑える酵素を作り出す。未感染の細胞と結合すると、
RNA分解酵素が活性化される。これは、ウィルスが侵入し、遺伝情報であるRNAを放出した時に分解してしまうので、ウイルスは増殖できない。元々、インターフェロンは、必要に応じて、体内で作り出されるのだが、慢性化した肝炎を治すには量が足りない為、それを助ける為に、体外から補充するのである。〈分類〉
IFN-
α……主に白血球が産生IFN-
β……線維芽細胞が産生IFN-
γ……主にTリンパ球が産生〈作用〉
肝炎の治療には、主に
〈目標〉HBe抗原を陰性化し感染力を弱め、肝炎を抑えて、肝硬変への進行を止める。
〈副作用〉
効果がある反面、かなりの副作用がある。〈投与方法〉
(1) 4
週間連日投与(2)
週2~3回の間欠投与
②アデニン・アラビノシド(
Ara-A)――DNAウィルスに対してのみ有効アデシンと拮坑的細胞内に取り込まれ、ウィルス
治 療 と 予 後 (型分類別)
A型肝炎
A型は慢性化しないので、安静な姿勢をとり、食事に気を付ける。場合によって、補液を受ける。
B型肝炎
急 性
初期は、原則入院である。 安静な姿勢をとり、食事に気を付けた生活を心掛けるが、急性期は、食欲不振、嘔吐の症状があるので、食事の投与は無理をせず、補液を行う。
慢 性
〈治療目標〉
・
HBe抗原の陰性化・
HBe抗体へのセロコンバージョン(seroconversion)〈治療方針・生活〉
慢性の場合は、激しいスポーツを避ければ、普段通りの生活で良い。
近年の食糧事情は良いので、牛乳
1本、豆腐半丁程度副食に加える程度で良い。但、酒は禁止である。
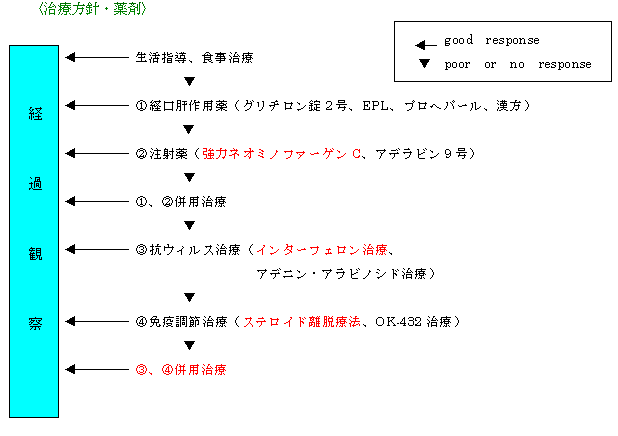
C
型肝炎C
型は、感染後、慢性化、劇症率が高く、その後、肝硬変、肝癌になる確率も高い。従って、劇症肝炎への移行、および慢性化防止が重要となる。急
性安静臥床のスケジュール、食事治療、補液、一般的薬物治療メニューは、
慢
性〈治療方針・生活〉
中等度以下の労働は可能であり、GPTの値によっては、テニス等のスポーツも可能である。
食事は、バランス良い食事を心掛け、飲酒は原則的禁止である。
〈薬剤治療〉
・一般肝作用薬
・免疫調整薬(漢方を含む)
・抗ウィルス薬――
強力ネオミノファーゲンC(SNMC)副腎皮質ステロイド
インターフェロン
C型肝炎の場合、インターフェロンの治療が一般的に有名である。
参考文献:ウィルス肝炎・渡辺明治・永井書店(
1993)参考
URL :http://www.cty-net.ne.jp/~shige/