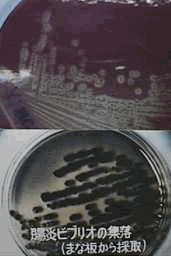1.腸炎ビブリオの特徴について
〈食中毒の分類〉
|
細菌性食中毒 |
感染型 |
サルモネラ |
||
|
腸炎ビブリオ |
||||
|
病原性大腸菌 |
||||
|
カンピロバクタ− |
||||
|
毒素型 |
黄色ブドウ球菌 |
|||
|
ボツリヌス菌 |
||||
|
中間型 |
ウェルシュ菌 |
|||
|
セレウス菌 |
||||
|
ウィルス性食中毒 SRSV(小型球形ウィルス) |
||||
|
自然毒食中毒
|
植物性
|
毒きのこ |
||
|
植物毒 |
||||
|
カビ毒 |
||||
|
動物性 |
フグ毒 |
|||
|
化学性食中毒 |
||||
|
その他の食中毒(アレルギ−様食中毒) |
||||
〈腸炎ビブリオ食中毒〉
しらす干しによる食中毒が1950年大阪で発生した際、藤野らはその原因菌として
Pasteurella parahaemolytica を分離命名した。国立横浜病院の食中毒の原因菌として滝川は1956年3%食塩添加によりよく発育する菌を分離し、Pseudomonas enteritis と名付けた。その後この両者の分離菌は一致していることが判明し、食塩がないと発育しないので一時期『病原性好塩菌』と呼ばれたが、1963年その学名はVibrio parahaemolytics ,和名は腸炎ビブリオと決定された。従来病因物質不明とされていた食中毒の大多数がこの菌を原因菌とすることが明らかになり、我が国の食品衛生上この菌の発見は大きく貢献した。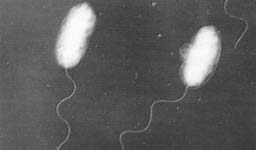
腸炎ビブリオ