陰部ヘルペス(性器ヘルペス、陰部疱疹)
Ⅰ.原因
<病原体>
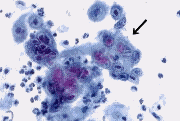
単純ヘルペスウイルス(
Herpes Simplex Virus:HSV)は,DNAウイルスで,1型(HSV-1)と2型( HSV-2)の2亜型に分けられている。HSVの特徴は,初感染後体内に持続感染(潜伏感染) することである。初感染の多くは不顕性感染で,顕性,不顕性を問わず初感染後は神経節(1型は三叉神経節、 2型は仙骨神経節が多い)に潜伏感染する。疲労,妊娠,怪我,熱性疾患生理的異常、各種感染症、心理的ストレス等を引き金とする免疫機能低下時に、ウイルスが再活性化されると,口唇周辺や陰部など特定の皮膚部位に水疱を生じる(回帰性ヘルペス)。単純ヘルペスウイルス(単純性疱疹ウイルス)が感染し、生殖器(性器)付近に発症したものを性器ヘルペスといい、口腔周辺に発症したものを口唇ヘルペスという。従来、口唇ヘルペスは1型、性器ヘルペスは2型と言われていたが、現在では、1型、2型、どちらでも性器ヘルペスが起こり得ることが知られている。
(上写真は水疱底から採取した感染細胞。(パパニコロウ染色))
<感染経路>
HSV1型は主に唾液を介して、乳幼児期に感染し、成人の約
70~90%、HSV2型は主に膣分泌液と精液を介して、思春期以後に感染し、成人の約20%が感染し、抗体を保有している。初感染の場合
7~12日間、再発の場合4~7日間、分泌液中にウイルスが排出され、他人に感染させることがあるとされているが、感染後発症しなかった人の唾液中からもウイルスが検出されているので、正確に決めることはできない。性器ヘルペスはセックス以外でも感染するか
?一般的に性交渉により感染するが、手や物に付着したウイルスも数時間感染力があると言われる。保菌者が口中に感染している場合はキスなどの接触でも感染の恐れがある。
思い当たる行為が無くて症状が出る場合もあるが、これは以前のセックスで感染して体の中に潜伏していたウイルスが過労やストレスで活性化したためである。セックス以外でも性器をなめることで菌がうつり、口の回りに水泡ができることもある。
感染すると3日~2週間ほどで外陰部や膣にペニスに米粒大の赤い水泡が出来る。感染初期に多少の不快感や微熱があることもあるが気がつきにくい。病状がすすむと水泡が多発し、破れてじくじくした潰瘍になり激しい痛みを感じる。外陰部が腫れ歩行困難なほど痛むことも。一度感染すると免疫力の低下などにより再発する可能性が高いが、きちんと治療すれば症状は消える。同じヘルペスでも口のまわりに出来る口唇ヘルペスもあるが、これもオーラルSEXによって陰部にも感染する。
Ⅱ.症状
性器ヘルペスは、外部から入ったウイルスによる初感染と、仙椎神経内に潜伏しているウイルスの再活性化による再発の二つの場合がある。
<男の人はどうなるの?>
男性の病変部位は包皮、冠状溝、亀頭であるが、肛門性交を行っている場合には、肛門や直腸にも発生する。
<女の人はどうなるの?>
女性の病変部位は陰唇、膣前庭、子宮頚部であるが、肛門性交を行っている場合には、肛門や直腸にも発生する。

初感染では、感染後約一週間で、外陰部に小水泡が単発ないし集簇的に多発する。小水泡は、まもなく破れて浅い潰瘍となり、治癒するまでに2~4週を要するが、自然に治癒する。しかし、治癒後も月経、性交その他の刺激が誘因となって、再発を繰り返す。再発疹は外陰部のほか、臀部、大腿にも生じる。
女性では、これらの他に、HSVの初感染による急性型があり、炎症症状が激しく、激痛を訴えるが、急性型は再発性とはなり難い。
左写真は大小の水疱をみる局所。 http://www.hakodate.or.jp/akiyama/knowledges/STD/std.htm
<赤ちゃんへの影響は?>
産道感染等による新生児のヘルペスウイルス感染症は、ヘルペスウイルスが細胞から細胞へと直接感染していくため、母親からの移行抗体による発症の予防が困難であり、極めて重篤な病態を示し、しばしば致命的となることがある。
新生児ヘルペス
とは…主に母子感染によって発症する。生後
14日以内に発熱、黄疸、呼吸障害、出血傾向が現われる。半数に中枢神経症状を伴い、致命率は80%にも達することがある。
Ⅲ.検査・治療について
<怪しい…と思ったら>
まず検査に行ってみよう!!HSV
感染症の診断法には,ウイルスやウイルス抗原を直接証明する抗原検査と血清抗体の上昇によって診断する血清検査とがある。抗原検出法は,ウイルス 分離をはじめ,病変部より得た細胞にHSV抗原を蛍光抗体法(FA)を用いて証明したり,モノクロ抗体を用いたシェル・バイアル法がありこの方法は特異性が高い。また遺伝子 検査としてin situハイブリダイゼーション,PCRなどによる方法があり,ヘルペス脳炎,新生児ヘルペス感染症などの早期治療により救命率を上げることが期待されて いる。抗
HSV抗体の測定法として,EIA法は感度が高くまたIgG,IgM抗体の分別測定も可能であるが,特異性は劣る。中和法はEIA法に比べ感度的には落ちるが特異性は高い。また中枢神経疾患の場 合EIA法のIgG補促法が有用であり,その特性から目的に応じて使い分けられる。以上から血清学的検査は,主として初感染の診断に有用であるが,中枢神経感染の診断や感染
HSVの型別推定にも応用されている。http://www.wise.or.jp/yuchan/new_ninsin/ninbyou/00204.html
検査方法:
http://www.srl-inc.co.jp/TESTCOREWEB/default.htm http://www.srl-inc.co.jp/TESTCOREWEB/indexhtml/index05XX1.html検査基準値→
http://www.healthnet.or.jp/kenkonet/shoziten/menu/hb2/p445.html
<どんな治療をするの?>
治療薬には、アシクロビルやビダラビン(Ara-A)がある。アシクロビルは、ヘルペスウイルスが自らの核酸合成のために持つ特殊な酵素チミジンキナ-ゼによってリン酸化されてはじめて活性化し、ヘルペスウイルスの核酸合成を阻害する。このため、ヘルペスウイルスが感染していない正常ヒト細胞内では、ほとんどリン酸化されることなく、活性化されないので、ヒトに対する毒性は極めて少ないが、ヘルペスウイルス以外のチミジンキナーゼを持たない非ヘルペス属ウイルスには無効である。
再発予防には、アシクロビルの少量連続投与が検討されている。
急性型で髄膜刺激症状が強いもの、疼痛の激しいもの、新生児の全身性ヘルペスウイルス感染症には、静注用のアシクロビルが効果的である。
対症療法として、局所の痛みに消炎鎮痛薬の投与、局所麻酔剤の塗布が行われる。
<どれくらいで治るのかな?>
軟膏と飲み薬で
1~2週間で治る。重度の場合は入院治療が必要。治療にはきちんと保険が効く。受診科は泌尿器科、婦人科。
(参考)
口唇ヘルペス(HSV-1感染症)
HSV1型ウイルスは、乳幼児期に感染することが多く、大部分は無症状に終わるが、1~10%は発症し、口腔咽頭粘膜に水疱を生じる歯肉口内炎のほか、時に角結膜炎、髄膜脳炎を生じる。
ヘルペスウイルスによる髄膜脳炎は、日本脳炎の発生が減少した現在、ウイルス脳炎としては最も頻度が高く、かつ重篤であり、小児では、しばしば致命的となるだけでなく、成人でも髄膜脳炎治癒後に重度の障害を残すことがある。初感染時には口腔内の歯肉口内炎が多いが、再発時には口唇やその周囲の顔に発赤で囲まれた水疱を生じる口唇ヘルペスが多い。いずれも数日で治癒する。
髄膜脳炎は普通初感染時に起こり、再発時に起こることは極めて希である。
単純ヘルペス脳炎
急性ウイルス性脳炎の中で頻度が高く主として1型ウィルスによる。
発症年齢は新生児から成人であり、どの季節にも起こる。年間発生はわが国では推定
300‐400件である。初感染時や免疫能の低下している時には重症化する。臨床経過は突然の発熱、けいれん、意識障害(幻覚、意識混濁、昏睡)、頭痛、吐気、嘔吐などの多彩な症状を示す。ウィルス性脳炎のなかで最も予後不良である。
http://www.mars.dti.ne.jp/~frhikaru/std/std.html#3http://chiba.cool.ne.jp/mioh/std.html#
ヘルペス http://shibuya.cool.ne.jp/littleheaven/bb.html