
1.細菌とは
細菌とは原核細胞からなる微小な単細胞生物。ふつうは細胞の分裂で増殖する。バクテリア
ともよばれる。細菌の大半は
1〜10μm足らずである。エネルギーの産生や栄養を摂取する方法は多岐におよぶ。空中、地中、水中、氷から熱い温泉まで、ほとんどすべての環境に生息する。深海底の熱水
噴出口さえ、酸素の代わりに硫黄を代謝する細菌のすみかである。ほとんどすべての食品

細菌の組織
生物の
5界分類法では、細菌は細胞内に核膜をもたない生物で構成されるモネラ界にふくまれ、およそ1600種が命名されている。一般的には、(
1)球菌、桿菌、螺旋(らせん)状のスピロヘータといった形状、(2)細胞壁の構造、(3)識別染色するグラム染色法、(4)酸素の有無によって増殖する能力(好気性細菌と嫌気性細菌)、(5)代謝または発酵の能力、(6)不利な環境で芽胞とよばれる休眠胞子をつくる能力、(7)表層成分の免疫特性、(8)核酸の近親性、などの特徴を基本に分類される。もっとも広く採用されている分類法では、細菌は細胞壁の特徴を基本として以下の
4つに大別される。(1)グラム陰性型のうすい細胞壁をもつグループ、(2)グラム陽性型のあつい細胞壁をもつグループ(グラム染色法で脱色されるものをグラム陰性型、そまるものをグラム陽性型という)、(3)細胞壁がないグループ、(4)細菌の細胞壁は糖とアミノ酸が結合したペプチドグリカンでできているのがふつうだが、これ以外の物質でできためずらしい細胞壁をもつグループ。最後のグループには、古細菌という特殊環境をこのむ一群がある。この一群には、二酸化炭素と水素からメタンをつくる完全な嫌気菌(偏性嫌気性細菌)であるメタン細菌、高い濃度の塩分で成長する好塩細菌、硫黄に依存する極端な好熱性細菌である好温好酸性細菌がふくまれる。最近の生化学研究によって、古細菌は他の細菌とことなり核膜をもつ真核生物の細胞と共通点が多いことがわかってきた。
細菌の
4つの大きなグループは、さらにおよそ30に区分され、さらに多くの目、科、属にわけられる。たとえば第1のグループのスピロヘータは、グラム陰性型細胞壁と、細胞壁と細胞膜の間に運動をおこなうための軸糸をそなえた、細長い螺旋状の細菌である。梅毒をひきおこすトレポネマ・パリズムはスピロヘータの一種で、スピロヘータ目スピロヘータ科に属する。すべての細菌が運動するわけではないが、運動できるものは一般的に鞭毛(波動毛)によってスクリュー式に推進される。鞭毛は、細胞全体か、片端または両端から、
1本ずつあるいは房状につきでている。鞭毛が回転する方向によって、前進したりその場で旋回したりする。進行と旋回の持続時間は、細菌の膜にある受容分子(レセプター)に関連している。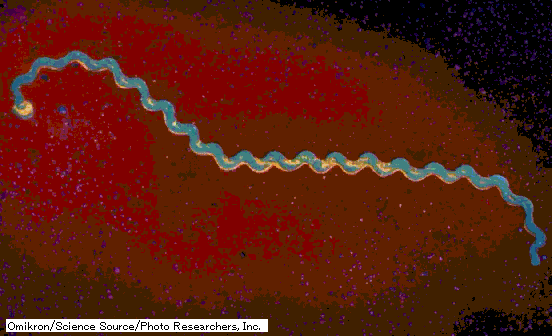
細菌の作用
細菌には
2つの主要なグループが存在する。動物の死体や枯れた植物の表面にすむ腐生細菌類と、生きた動植物の表面や内部にすむ共生細菌類である。腐生細菌類が重要なのは、動植物の遺骸を構成要素に分解して、植物の肥料にできるからである。共生者としての細菌が消化管や皮膚をふくむ人間の多くの体組織の一部に正常に存在し、消化吸収などの生理プロセスに不可欠な場合もある。このような関係を相利共生という。また共生者が生きた宿主から栄養をえるが、深刻な被害をあたえることはない場合、片利共生という。3番目のタイプが寄生で、とりついた動植物に死をもたらすことがある。細菌は、肉や野菜、牛乳や乳製品などの劣化に関係する。細菌の作用でこれらの食品が変質し、食べられなくなる。食品の中で細菌が増殖すると、黄色ブドウ球菌やボツリヌス菌がひきおこすような食中毒につながる。一方、細菌は多くの産業で重要な役割もはたしている。さまざまな種の発酵能力が、味噌や醤油やアルコール飲料などの醸造や、チーズやヨーグルトといった乳製品や漬物類の製造につかわれている。ほかに、なめし革、タバコ、牧草のサイロ処理、繊維生地の処理、医薬品、酵素類、多糖類、洗剤の製造にも細菌はかかせない。
細菌はほとんどすべての環境に生息し、さまざまな生物学的プロセスに貢献している。たとえば、死んだ魚に燐光を発生させたり、干し草の山やホップ倉庫で自然発火するほどの熱を生じたりする。ある種の嫌気細菌は、セルロースを分解することによって、沼地からメタンなどを発生させる。酸化プロセスによって沼鉄鉱、黄土、マンガン鉱石の堆積をたすける細菌もある。
細菌は、土壌の性質や成分に大きな影響をあたえている。細菌は、有機物である動植物の遺骸や無機的な岩の粒子を完全に分解してしまう。この作用によって、膨大な量の植物の栄養物ができる。さらにマメ科植物は、その根と共生して窒素を固定する根粒を成長させる根粒細菌の助けをかりて、窒素含有量をまして土壌を肥沃にする。
植物の生長に不可欠である光合成が、まず細菌で確立したのはほぼ確かである。植物の葉緑素(クロロフィル)と、分子構造や色の少しちがうバクテリオクロロフィルをもつ紅色細菌などが、古い光合成のタイプを代表していると考えられる。
病原菌
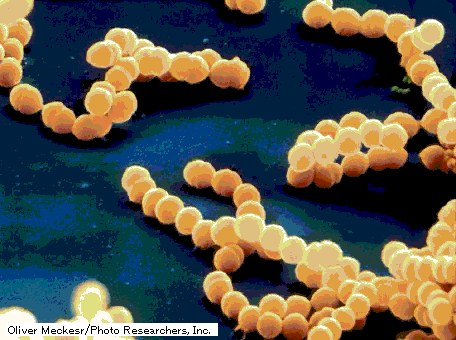
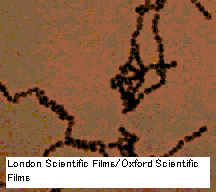
連鎖球菌 溶血性連鎖球菌
細菌が体組織にもたらす病原性の影響は、以下の
4つに大別できる。(1)ノビ菌によってひきおこされるガス壊疽のように、組織局所の破壊に細菌が直接作用する影響。(2)細菌の集団が血管をつまらせ感染性の塞栓をひきおこす場合のような、機械的影響。(3)結核でできる肺の空洞や、リウマチ熱において体自身の抗体で心臓組織が破壊されるような、感染した特定の細菌への体の反応の影響。(4)細菌がつくる毒素がひきおこす影響。毒素は一般的には種によってちがう。たとえば、ジフテリアをひきおこす毒素は、コレラ菌の毒素とはことなる。
抗生物質
ある種の菌類や細菌をふくむ、さまざまな微生物は、別の細菌にとって有害な化学物質をつくる。ペニシリンやストレプトマイシンをはじめとするこのような物質を抗生物質という。抗生物質は細菌を殺したり、細菌の成長や増殖を阻止する。近年、抗生物質は細菌による病気を制圧するうえで医学的に重要な役割をはたしているが、抵抗性をえてしまった耐性細菌の出現が重大な問題となることもある。