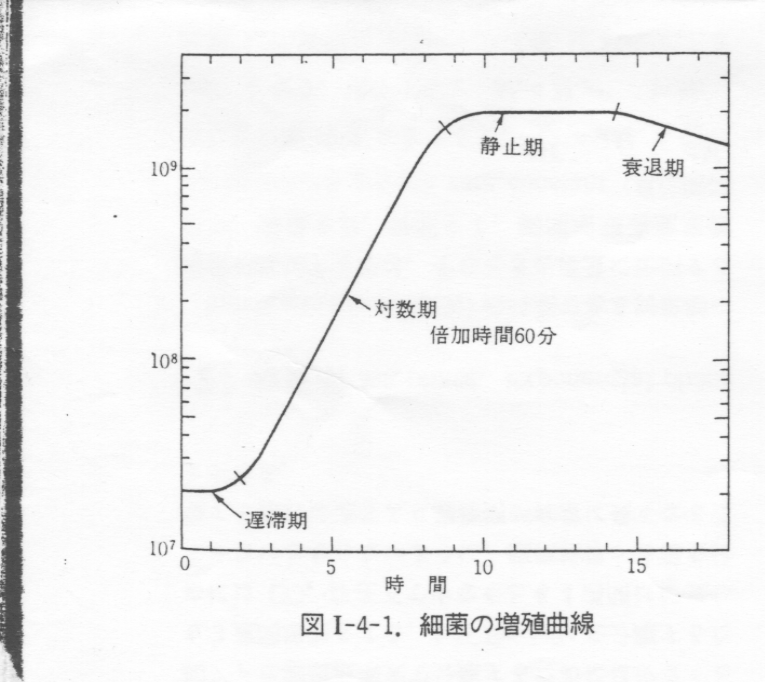
4.増殖曲線
細菌を適当な培地で増殖させると対数的に増殖し、ある程度まで増殖すると増殖がとまる。はじめに接種する菌が同じ培地で対数的に増殖している菌の場合は直ちに対数的に増殖するが、増殖が終わった静止期の菌を接種した場合には直ちに増殖は始まらず遅滞期(
lag phase)とよばれる時期ののちに増殖し始め対数期(log phase)に入る。対数期が終わると増殖が止まり静止期(stationary phase)になり、放置しておくとだんだんと菌が死滅する衰退期(phase of decline)に入る。
普通ブイヨンのような完全培地で増殖した静止期の菌を最小培地にすると、同じ完全培地にしたときより、遅滞期が長くなる。それは完全にはアミノ酸が含まれていて、その培地で増殖した菌の細胞内には、ある程度のアミノ酸のプールはあるが、アミノ酸合成に必要な酵素が誘導されていないので、最少栄養培地に接種されたときにはまず、既存のタンパクの一部を分解して生じたアミノ酸からアミノ酸合成に必要な酵素をつくり、その酵素で必要なアミノ酸を合成して一般的なタンパク合成を行うからである。それに比べ同じ完全培地に接種されたときにはそのようなアミノ酸合成の必要がないので遅滞期がより短くなる。
balanced growth
(後出)の時期である対数期に菌量が増加する率は、その時の菌量に比例するので、菌量をM、時間をt、瞬間増殖速度定数(単位時間あたりの増加)をαとすると、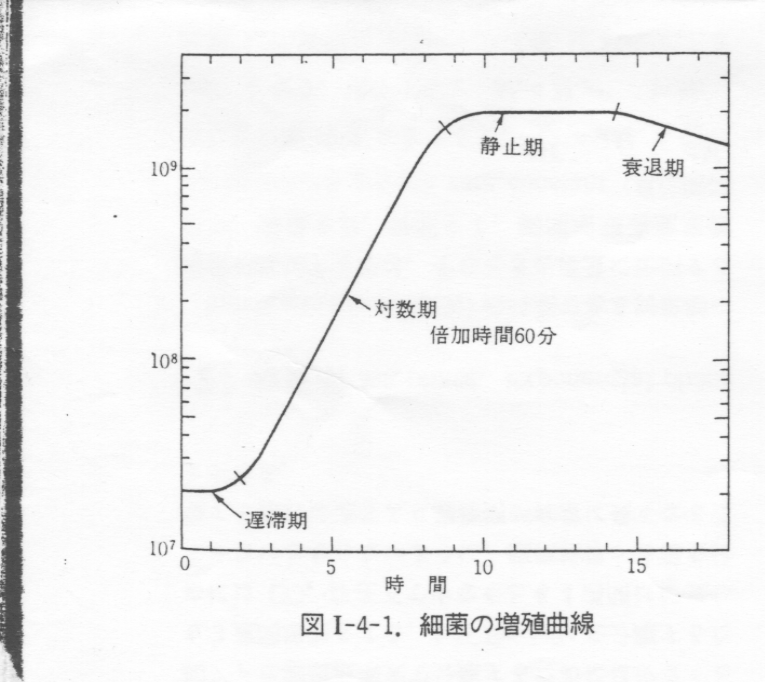
瞬間世代時間、τは、
t=0のときの増殖速度1個の細菌が
10階分裂すると、21?=1024(≒103)になり、20世代で約10?、30世代で約10?である。比較的増殖が速い腸内細菌科の細菌を完全培地で増殖させると倍加時間は20分であるが、10?になるのに10時間しかかからない。同じ菌を最少栄養培地に植えると倍加時間が約60分になるが、その時には10?になるのに20時間かかる。寒天平板で1個の集落を形成するのに
10?~10?の細菌が必要であるので、倍加時間が60分でも24時間培養すれば集落が出現するし、完全培地の場合は7~8時間で十分である。倍加時間がもっとも短いものは10分くらいである。対数期はある一定の生菌数になると終わる。たとえば完全培地で培養すると、大腸菌では2~4×10?CFU/ mlまでであるが、培地を工夫することによりさらに増菌させることができる。図Ⅰ-4-1 に示した特別栄養強化培地では
対数期の菌において、増殖にとって重要な機能を触媒しているものの合成が止まったとき、たとえばリボソームの合成が止まったときには既存のリボソームでタンパク合成をし、分裂をしていくことになるので、いわゆるlinear growthをすることになる。算術方眼紙で直線となる増殖を示し、やがては増殖が止まる。
(3)静止期
stationary phase培地中の発育は、いわば閉鎖系であるため、
新生菌と死滅していく菌との間に均衡が保たれ、生菌数が一定した静止期(
stationaryphase)が、しばらく続く。この静止期では、RNAポリメラーゼの
(4)衰退期
phase of decline①有害物質の蓄積
②pH の強い変化 などにより、
細菌の自己融解が進行し、死滅していく菌が増加していく(衰退期
phase of decline)。この衰退期に入ると、菌体は長くなったり、ふくれたり、変形したりして、やが ては、死滅する。その時の培地・菌種・環境などによって死ぬ速度は異なるが、肺炎双球菌は、2~3日で死に絶え、大腸菌は数ヶ月も生き長らえることができる。