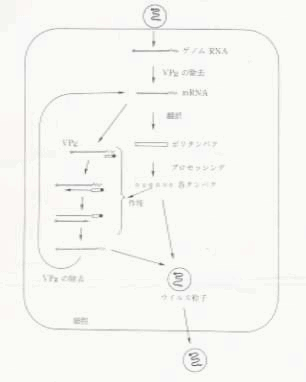
免疫グロプリンスーパーファミリーの特徴を持つもつレセプターを介し、ポリオウイルスは細胞に感染する。(図)ポリオウイルスの
<ポリオウイルスの構造の特徴と感染方法について>
ポリオ(急性灰白髄炎)とは
「小児マヒ」とも呼ばれ、
1960年代まで世界的に蔓延し、小児に多く感染した。感染者は死亡するか、生き延びても手足の麻痺が後遺症としてのこる。ウイルス性の感染症である。
ポリオウイルスの特徴
ポリオウイルスは
1本鎖のRNAを遺伝子として持つ。正二十面体で、直径が28nm程度と、RNAウイルスの中ではもっとも小さい。動物ウイルスで最初に結晶化され、またRNAが感染症を示すとわかった最初のウイルスである。
ポリオウイルスの複製
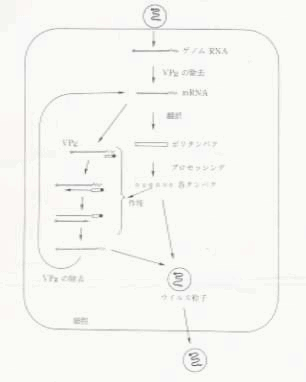
免疫グロプリンスーパーファミリーの特徴を持つもつレセプターを介し、ポリオウイルスは細胞に感染する。(図)ポリオウイルスの
ポリオウイルス感染
1.臨床
ウイルスに感染しても、大部分(
99%)は不顕性感染で、症状はなく抗体を獲得しウイルスは除去される。一部は不全型としてかぜ様の症状を示す。まれに、髄膜刺激症状を伴う非麻痺型となる場合がある。少数が、弛緩性麻痺を伴う麻痺型に至る。小児より成人のほうがその危険性は高いとされている。
2.感染経路
ポリオウイルスは口から入り、腸管や咽頭の上皮細胞に感染し増殖する。次にパイエル板や扁桃腺のリンパ組織に広がり、リンパ節を経て血中に入り全身に広がる。血液脳関門を突破し、標的細胞である神経細胞の末端から軸策を通って中枢神経に入る経路も想定される。脊髄前角の運動神経細胞などに感染し、細胞を破壊し、四肢の麻痺を生じる。
3.ポリオウイルスの3つの血清型(Ⅰ,Ⅱ、Ⅲ)
ポリオウイルスは3つの血清型
[Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ] に分けられる、ピコルナウイルス科のエンテロウイルス属に分類される。30
歳までに、ポリオウイルスの3型すべてに対する抗体を獲得する。千例に1例の割合で、ウイルスが脊髄前角に病変を作り、もっとも重篤な場合、麻痺とその後遺症をもたらす。顕性型は主として雨季におこる小流行により、爆発的に増加する。
症状が重篤で、流行を起こしやすいのは、Ⅰ型が圧倒的に多く、Ⅱ型によるものは殆どない。一方、生ワクチン接種後の医原性ポリオはⅡ型とⅢ型が多い。