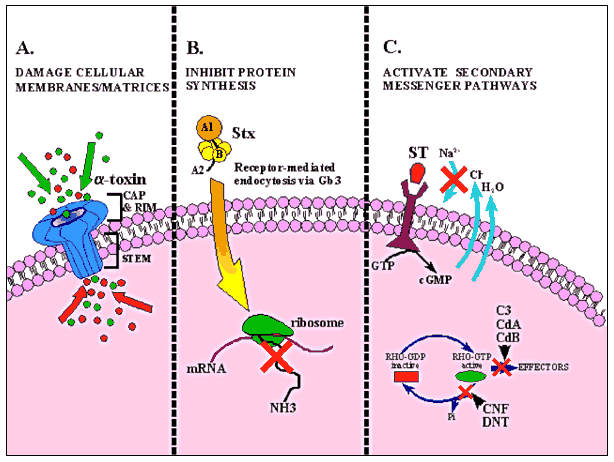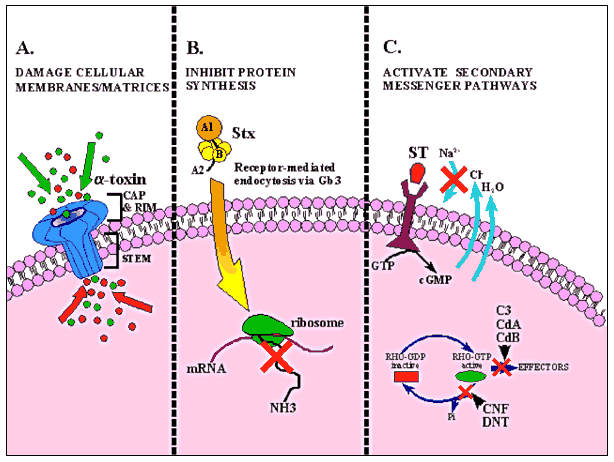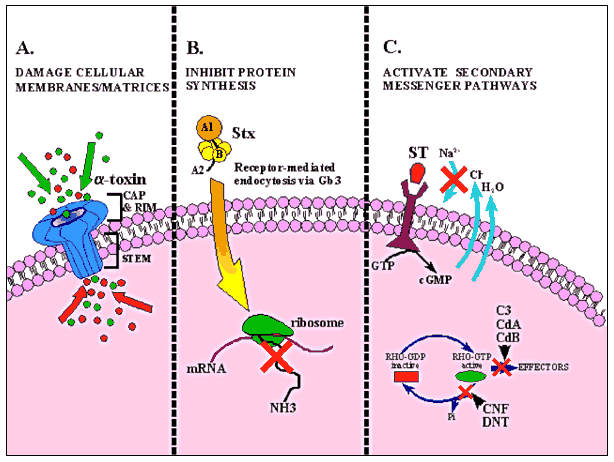外毒素の作用機序
近年、種種の毒素が酵素活性を持っていることが次第に明らかになっているが外毒素の作用は多様であり、まだ不明の点も多い。このため1つの基準で分類することは困難である。戸田新細菌学では、作用機序、標的となる臓器・細胞・分子・、毒性の違いなどから以下のように分類して解説してある。
- 細胞膜に作用する毒素
①膜を貫く孔を形成する毒素
pore-forming toxin
②リパーゼ活性を持つ毒素
③膜の酵素に作用(活性化)する毒素
タンパク合成を阻害する毒素
①28S rRNA N-glycosidase活性
②
ADPリボシル化
腸管毒enterotoxinまたは下痢毒
①cytotonicな作用を持つ毒素
②
cytotoxicな作用を持つ腸管毒
③黄色ブドウ球菌が産生する腸管毒staphylococcal enterotoxin(SE)
神経毒neurotoxin
心臓毒
皮膚毒
- 加水分解酵素
- スーパー抗原
superantigenとなる細菌毒素
1.
細胞膜に作用する毒素
①膜を貫く孔を形成する毒素pore‐forming toxin
毒素分子が重合して細胞膜を貫通する管を形成し細胞を破壊する。
8.5~10nm、内径2~3nmの孔を形成する。 〔論文より〕このα毒素は、オリゴ化して孔を形成する細胞毒素の原型と考えられ、α毒素8量体のキャップ領域(帽子の部分)とリム領域(縁の部分)は細胞膜の表面にある。一方、ステム領域(柄の部分)は膜の輸送チャネルとして働く。
レンサ球菌のストレプトリジンO・・・膜上のコレステロールと結合し毒素との複合体がリング(外径約30nm)を形成し細胞膜に入り込む。酸素に触れると可逆的に不活化され、SH基を持つ化合物(システイン、グルタチオンなど)により活性化されるので、SH細胞毒と呼ばれる。
②リパーゼ活性を持つ毒素
ウェルシュ菌のα毒素・・・ホスホリパーゼCである。細胞膜を構成するレシチン含有リポタンパクに作用して膜を破壊する。
ブドウ球菌のβ毒素・・・リン脂質分解酵素の1つスフィンゴミエリナーゼである。
ブドウ球菌のδ毒素・・・ホスホリパーゼである。この酵素活性により界面活性作用が現れ細胞膜が崩壊する。
③膜の酵素に作用(活性化)する毒素
ブドウ球菌ロイコシジンと緑膿菌ロイコシジン・・・溶血活性はないが好中球やマクロファージの膜酵素に作動して膜障害を引き起こす。細胞のレセプターに結合後、前者は膜のホスホリパーゼA2を活性化して膜のK+透過性変化を招き、後者は膜のホスホリパーゼCを活性化した結果、リソソーム酵素を細胞内に放出して、各々白血球の破壊を起こす。ロイコシジンは炎症部位に浸潤してくる白血球を破壊するため、生体防御に抵抗する細菌側の因子として重要!
タンパク合成を阻害する毒素
①28S rRNA N-glycosidase活性
赤痢菌の志賀毒素と志賀毒素様毒素…この毒素のAサブユニットは28S rRNAの特定の1個のアデニンを遊離させる活性をもつ。その結果、アミノアシルtRNAが60Sリボソームに結合するのを阻害してタンパク合成を阻害する。Bサブユニットに対するレセプターは細胞表面のグリコリピドである。
②ADPリボシル化
ジフテリア毒素と緑膿菌のエキソトキシンA…ペプチド延長因子EF-2をADPリボシル化することによりそのトランスロカーゼ活性を阻害し、タンパク合成を止め、細胞を障害する。
3.
腸管毒または下痢毒
①cytotonicな作用を持つ毒素
コレラ毒素(cholera toxin:CT)と毒素原性大腸菌の易熱性毒素(heat-labile toxin:LT)…腸管粘膜上皮細胞の膜ガングリオシドGM1に結合し、一部が膜の内側に達してアデニレートサイクラーゼを持続的に活性化し、膜のcAMPの量を増加し、上皮から水・電解質を大量に分泌させ水様性下痢を引き起こす。
毒素原性大腸菌の耐熱性腸管毒(heat-stable enterotoxin:ST)とYersinia enterocoliticaの腸管毒・・・グアニレートサイクラーゼに直接結合して持続的に活性化し、細胞内のcGMPの量を増加させ下痢を引き起こす。
②cytotoxicな作用を持つ腸管毒
志賀毒素と志賀毒素様毒素・・・タンパク合成阻害毒素の項で既述したがその細胞傷害活性により出血性下痢を引き起こす。
③黄色ブドウ球菌が産生する腸管毒staphylococcal enterotoxin(SE)
腸管から吸収された後に中枢神経に達し、嘔吐や水の吸収阻害による下痢を引き起こす。その作用機序の詳細は不明であるが、スーパー抗原としての作用を有する。
4.
神経毒
破傷風菌のテタノスパミン…脊髄前角の運動神経細胞のガングリオシドGT1とGD1Bに結合し、それを亢進させて筋肉の強直性痙攣を起こす。
botulinum neurotoxin…ボツリヌス菌が産生する毒素。神経筋接合部の運動神経末端からのアセチルコリンの分泌を抑制し、弛緩性麻痺を起こす。
Shiga neurotoxin…志賀赤痢菌が作る毒素。中枢神経系の小血管を傷害し、二次的に神経麻痺を起こす。
5.
心臓毒
腸炎ビブリオ溶毒素…90℃、10分の加熱にも耐える耐熱性蛋白で、赤血球を破壊するだけでなく、培養した心筋細胞に作用し心筋を収縮期で停止させる。生きた動物に投与するとペースメーカー細胞の自発興奮能がなくなり心拍動は停止する。本菌による食中毒で死者が出るのは主にこの毒素作用による。
6.
皮膚毒
黄色ブドウ球菌の剥離性毒素・・・表皮のデスモゾームを開離して表皮を剥脱させる。
- 加水分解酵素
タンパク分解酵素(細胞外マトリックスを分解する)やヒアルロニダーゼ、
Dnase(DNAを分解する)は、細胞膜を破壊するリパーゼ活性をもつ毒素とともに組織破壊を起こすので侵襲因子として重要である。黄色ブドウ球菌、レンサ球菌、クロストリジウム属など組織侵襲性の強い病原菌が産生する。またこれらの酵素は細菌の増殖に必要な栄養源やエネルギー源を宿主内で獲得するのに欠かせないもので増殖因子でもある。
- スーパー抗原
superantigenとなる細菌毒素
- 黄色ブドウ球菌の毒素性ショック症候群毒素
toxic shock syndrome toxin-1(TSST-1)、腸管毒staphylococcal enterotoxin(SE)、化膿レンサ球菌の発熱性外毒素(SPE)…MHCクラスⅡ陽性細胞(Bリンパ球、マクロファージ、Langerhans細胞、血管内皮細胞)のMHCクラスⅡ分子に結合し、おのおの一定のVβを表現するTリンパ球を非特異的に刺激する。大量のTSST-1やSEが産生されると、Tリンパ球が過剰に活性化され、大量のサイトカインが産生されて発熱、発疹、ショックなどの全身症状を引き起こし病態を修飾すると考えられている。
外毒素の作用機序の例
〔論文より抜粋〕
A.
膜を貫く孔を形成する毒素pore‐forming toxinの例
黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)のα毒素…結合とオリゴ化の後、マッシュルーム状のα毒素8量体のステム領域は標的細胞の中に挿入され、下図の赤と緑の矢印のようにイオンの流入、流出が起こり、膜の透過性が壊れる。
B.
タンパク合成を阻害する毒素の例
志賀毒素…ホロ毒素は酵素活性をもつAサブユニットと5つ結合したBサブユニットでできている。これが、グロボトリアシルセラミド(Gb3)レセプターを通して細胞内に入る。その時、AサブユニットのN-グリコシダーゼ活性が、28SリボソームRNAからアデノシン残基を遊離させる。その結果、蛋白合成が停止する。
C.
二次メッセンジャーが働く毒素の例
耐熱性腸管毒(ST)…グアニレートサイクラーゼに耐熱性腸管毒(ST)が結合すると、サイクリックGMP(cGMP)の増加を引き起こす。cGMPは電解質の流入に影響する。
ボツリヌス菌(Clostridium botulinum) のC3外酵素とクロストリジウム・デフィシル(Clostridium difficile)毒素 A と毒素B (CdA & CdB)…それぞれのADPリボシル化、グリコシル化によって、RHO‐GTP結合蛋白を不活性化する。
大腸菌のもつ壊死の要因となる細胞毒素(CNF)とボルデテラ(Bordetella)属の皮膚壊死毒素(DNT)…脱アミノ化によってRhoを活性化する。
(図1)