マラリア感染のメカニズム

蚊がマラリアを伝播するという大発見は,1897年8月20日に,ロナルド・ロス(Ronald Ross)によって,インドのSecunderabadでなされた。
(この発見の歴史的なことについてはここ
「マラリアの媒介者発見の歴史」を見てください。)マラリア原虫では、蚊の吸血に際し、人の流血中の雌雄の生殖母体
Gametocyteが口器から取り込まれる。雌雄の生殖体Gameteは蚊の中腸内で受精し、接合体Zygoteを形成する(有性生殖)。これは次に運動性のオオキネートOokineteとなり無数の胞子小体Sporoziteを作る(無性生殖)ということは前述したが、この胞子小体は、唾液腺に集まり、蚊の吸血の際に人に経皮的に注入される。蚊が唾液腺に感染力のある胞子小体を持つようになるまでには温度によっても異なるが、10日から15日を有する。マラリアの媒介蚊であるハマダラカの一部は、空缶や使い捨てられたタイヤなどの人工容器が増えたことによって大量発生してきている。人社会が媒介蚊の発生源を提供し、病気を生み出しているともいえる。
病原体に対する昆虫の感受性
①感受性とは
:ある病原体が昆虫に取り込まれ、その生体内で発育または増殖し、感受性を得手で伝播される場合、この昆虫はこの病原体の感染に感受性
Susceptibleであるという。これとは逆に、病原体が感受性を持つにいたらなかったときは、その昆虫は非感受性であるという。この感受性の有無は、昆虫の種類によって違う。マラリアの場合、多くの蚊の中で、ハマダラカの仲間だけが人マラリア原虫に対して感受性であり、イエカやヤブカに属する蚊は感受性がない。サルのマラリア病原体は、ヌマカの体内で、胞子小体形成が観察されているが、唾液腺への移行が見られない。また、ある病原体の異なる株に対して、同一種の昆虫が違った感受性を示す事が報告されている。ハマダラカの一種
An.quadrimaculatusは三日熱マラリア原虫P.vivaxおよび、熱帯熱マラリア原虫P.falciparumに感受性であるが、別のハマダラカ種An.punctipennisは前者には感受性を示すが、後者の株には非感受性である。また、別のハマダラカはAn.albimanusは同地域の三日熱マラリア原虫には感受性があるが、別の地域の三日熱マラリア原虫には感受性は示さない。病原体に対する昆虫種の感受性は、実験的に感染させて調べる事ができる。マラリア原虫では、この病原体を取り込ませた蚊のうち、唾液腺に感染型を保有するにいたった蚊の割合で求められる。②感染性を決める要因
《形態的要因》
:吸血昆虫の口器の形態の違い。吸血昆虫は一般的に上唇
-上咽頭、一対の大腮と小腮、下咽頭および、下唇からなる。蚊ではこれらが下唇を除いて注射針状の細い管をなし、それを直接皮膚の血管に刺して血液を摂取する。吸血時はその先端部を皮膚に密着させ、上唇-上咽頭および下唇の先端部でそれぞれの皮膚を前後に引っ張る。次いで、左右の小腮を皮膚に刺し、安定した状態で、大腮で左右に皮膚を引き裂く。このとき、皮膚の中の毛細血管が破れ、滲み出た血液を吸い上げるのである。このようにして吸血を行うが、その構造の違いによって吸血方法が異なる事によって、血液内の病原体のみしか摂取できなかったり、皮膚内に存在する病原体まで摂取できたりする。《生理、生化学的要因》
:生理的要素としては、昆虫の唾液腺の抗血液凝固因子
anticoagulantsの有無があげられる。この因子の有無は、中腸に摂取された血液が凝固される時間と密接な関係がある。血液凝固が速いと、同時に取り込まれた仔虫が閉じ込められ、発育場所へと移動できなくなる。《免疫的要因》
:いくつかの病原体に対して、種々の昆虫が体液中の血球細胞を介した免疫反応を示す事が知られている。
ⅰ
)殺微生物、あるいは微生物溶解因子を放出。ⅱ
)単細胞病原体の貪食作用。ⅲ
)血球細胞による多細胞病原体の囲包。ⅳ
)病原体表面に見られるメラニンの沈着。(
このすべてがマラリア原虫に対して免疫として働いているというわけではない。)
昆虫の生態
ある地域では普通数種のハマダラカが生息しているが、マラリアの媒介者として重要なのはそのうち数種である。特に熱帯地域において重要な種を表にあげるが、マラリア原虫の発育・増殖を支える能力(感受性)のほかに、人吸血嗜好性の強さ、生存率、発生数などが効率のよい媒介者であるかどうかの要因となる。
《吸血嗜好性》
マラリアのように昆虫の吸血行動が直接伝播に関わっているとき、その昆虫の吸血嗜好性がまず重要となる。感受性があっても、人を吸血しない種は、もちろん媒介者足り得ない。人も、多の動物も吸血する種では、人から吸血する相対的割合が、媒介者としての機能を左右する。
《生存率》
病原体が昆虫内に取り込まれて一定の発育、ないしは増殖をし、感染性をもつには最低ある日数を要する。この期間
extrinsic incubation periodは病原体の種類や温度条件などで異なるが、たとえば、三日熱マラリア原虫の場合は、ハマダラカの一種に取り込まれてから、胞子小体が形成されるまで、15℃で18日、21℃では15日、26℃で11日、32℃で9日をようする。蚊が吸血後この期間を生存できないようなときはこれは媒介者とはなり得ない。また、生存できる場合でも、その割合が低いと、伝播能は落ちる。アフリカのマラリア蚊An.arabiensisとAn.gambiae s.s.を胞子小胞を持っている割合で比較すると、前者のほうが1/15も小さい。これはAn.arabiensisの生存率が低く、人を吸血する回数が少ない事を示している。※マラリアの伝播には、外部形態では判別のつき難いいくつかの同胞種からなる群種が関与しており、それぞれの同胞種で、発生場所、動物嗜好性や家屋内侵入など吸血習性、殺虫抵抗性などが違う場合がある。このことは種媒介種の同定だけでなく、媒介蚊対策をしばしば困難にしている。アフリカのマラリア媒介蚊は最初は
1種と見られていたが、染色体の研究などによって生態的に異なる7種が含まれていることが明らかになった。マラリアなどの原虫は、媒介昆虫体内で多数の感染型に増殖するので、同一個体の昆虫で、続けて複数の人に感染しうる。さらに、人に注入された胞子小体をもとに、たくさんの原虫ができるので、ある程度の個体数でも伝播は比較的容易である。
感染の恒常的な維持に必要な蚊個体群の最小密度は、同一の病原体であっても、媒介昆虫種の感受性の度合いによって高低が見られる。マラリアの媒介蚊では、南インドのハマダラカ
An.culcifacis、中米のAn.albimanusおよび、An.aquasalisは感染性が低く、寿命も短いが、発生数が多いため、自然界では重要な媒介者となっている。
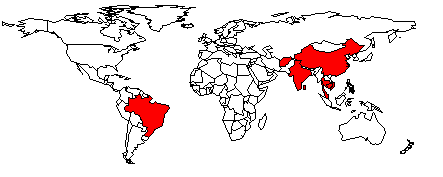
WHO
が第二次大戦後実施したマラリア媒介蚊対策は、当初はマラリア撲滅計画Malaria Eradication Programme、その後はマラリア防圧計画Malaria Control Programmeと呼ばれた。これは対策の目標が媒介蚊の根絶から感染が維持できないレヴェルまでの媒介蚊の個体群密度を低下させることに変わったことによる。蚊の防除
個人的には忌避剤を皮膚に塗布する(虫除けスプレー)。就寝時に蚊帳をはる。この場合、蚊帳に破れがあったり、蚊帳のつり方が不完全であると、破れた穴や裾から入るので注意が必要である。部屋に入ってきたかを蚊取線香や即効性の殺虫剤で殺すなどの対策もある。
就寝時間が早いと、蚊取線香が翌朝までもたないので注意する。一方、組織的な対策としては、蚊の発生源となる下水や水田などの環境整備および管理、殺虫剤や成長阻害剤を用いた科学的防除、蚊の幼虫の天敵となる捕食者(魚やオオカなど)や寄生虫(線虫、カビ、微胞子虫など)を利用した生物的防除、さらに、妊娠雄を放つ遺伝子的な防除などがあげられる。後者において、防除の目的、対象とする蚊の種類、媒介する疾病の特性、地域の環境的条件などによって用いられる方法は異なる。これらの方法を2つ以上組み合わせた、いわゆる総合防除対策が取られる場合が多い。
たとえば、
WHOが第二次大戦後に主導してきたマラリア媒介蚊対策の場合は、ハマダラカ雌性虫が人家内で吸血後、壁面で休むという習性を利用して、DDTなどの残留性の強い殺虫剤(その後、DDTはスミチオンなどの低毒性の有機燐などに置き換えられた)を屋内の壁面に年に2回散布して一部の国では効果を上げてきた。最近では殺虫剤を染み込ませた蚊帳やカーテンが蚊に対して忌避及び殺虫効果があると報告されている。しばらくすると
DDTでも死なない耐性原虫が出現してきたが、アメリカなどの一部の国ではそれが広がる以前に、大量にDDTを散布することによってマラリアを根絶することに成功している。